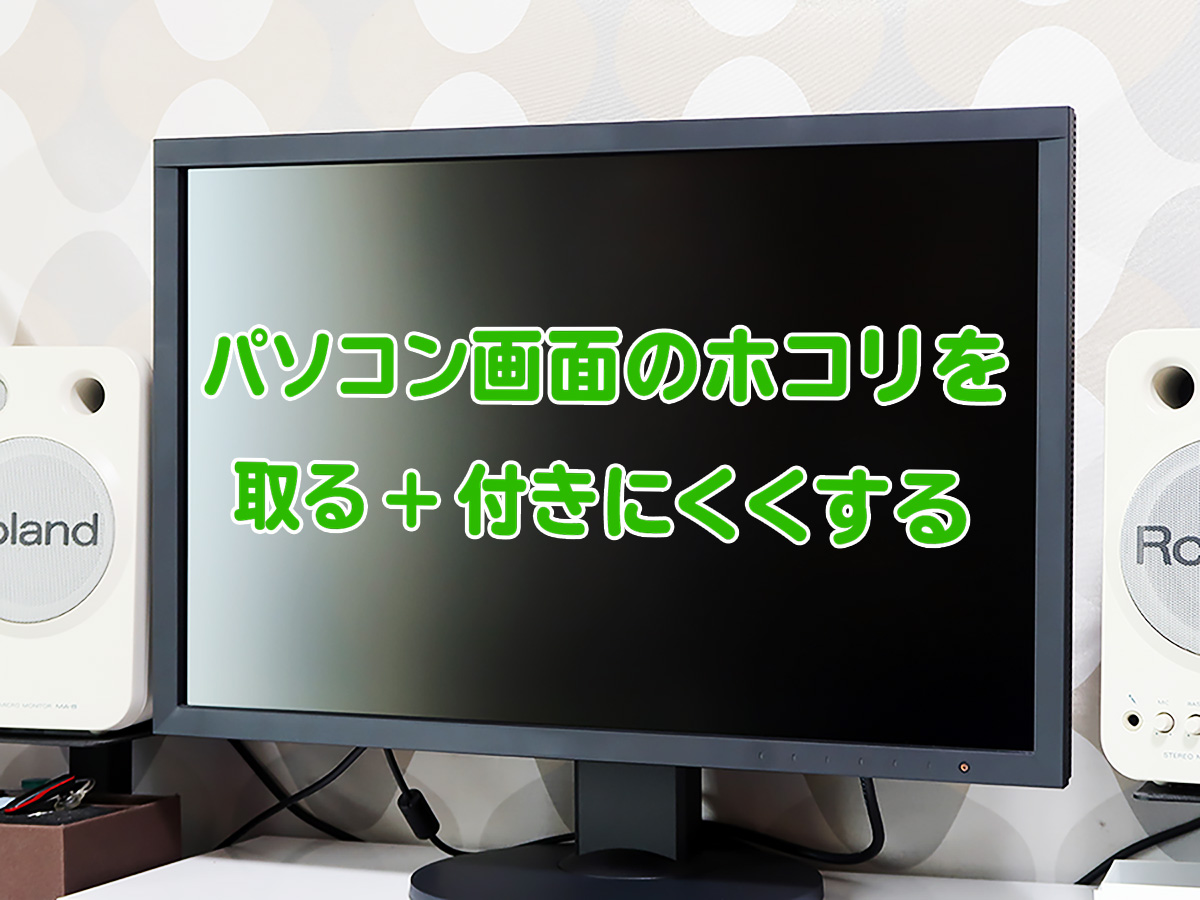鉢植えの植物を栽培するなら、忘れてはいけないのがコガネムシ対策。
コガネムシが土に産卵して、生まれた幼虫が植物の根を食い荒らすから、元気だった植物が突然弱ってしまったり、根がダメになって枯れてしまうんですよね。
私もこれまで大切にしていたベリーの木をコガネムシに枯らされたことがあるので、今はちゃんとコガネムシ対策をしています。
ということで、今回は「鉢底ネット」を使ったかんたんなコガネムシ対策を紹介します。
これが唯一のベストな方法というわけではありませんが、方法の1つとして参考にしていただければと思います。
まずは作業前の様子をチェック
現在私の家では、ブルーベリーとボイセンベリーの木を少しだけ栽培しています。

以前はもっと本数があったのですが、ある夏にコガネムシに徹底的にやられて木が減りました…。
ブルーベリーは不織布でカバー済み
これまでは「不織布」を使ってコガネムシ対策をしていたので、今回の作業前までこんなかんじでした。

不織布でもコガネムシ対策には十分な効果がありますよ。
不織布は着脱が面倒で、追肥や掃除・草抜きなどの管理がやりにくいし、見た目もブサイクだから好きにはなれませんでした。そこで今回鉢底ネットに更新です。
ボイセンベリーは無防備、早くやらなきゃ
それからボイセンベリーの木は、冬に植替えしてから初めての春を迎えるので、コガネムシ対策はこれから。

例年、コガネムシは5月中頃からやってくるので、早くコガネムシ対策をしないと奴らにやられてしまいます。
以前栽培していたラズベリーの木はコガネムシに壊滅させられました。
コガネムシ対策、鉢底ネットでやってみよう
コガネムシ対策の要点はたった1つ。
コガネムシは土にもぐって卵を産むので、もぐれないように土をカバーするのです。
というわけで、さっそく作業してみましょう。
用意するもの

1.鉢底ネット
自由に切って使える「プラスチック製の鉢底ネット」を使います。
ちなみに、「ロール状で売られているもの」よりも、私が使っているような「平らな状態で売られているもの」がお勧め。巻きぐせがないほうが、土の上に置きやすいです。
2.ハサミ
鉢底ネットはハサミで切れます。ものによってはすごく硬いことがあるので、力に自信がない人は「硬いもの用の万能ハサミ」を使うといいでしょう。
力が要らないよく切れるハサミを使うと曲線もきれいに切れますよ。
手順はかんたん
作業の様子を順番に紹介します。まずはブルーベリーの木から。
1.プランターに乗せて、はみ出す部分をカットする
こちらは難易度が高い「8角形」のプランターでの例。「丸い鉢」の例も下に続きますよ。
プランターに鉢底ネットを乗せて、はみ出す部分をカットします。

こんなかんじで、ぴったり。

直線にカットする時は、鉢底ネットのマス目を見て「どのマスから、どのマスまで切る」と確認すれば上手くいきますよ。
2.植物の根元に合わせて凹みを作る
鉢底ネットが平らに置けるように、植物の根元部分に合わせて切り欠きます。

スキマは小さいほど良いですが、鉢底ネットがガリガリ当たるようだと植物を傷つけます。
表面が硬い木なら心配ないですが、柔らかい植物の場合は鉢底ネットが触れない程度にスキマを空けてあげましょう。
将来的に、土からサッカー(新梢)が出てきた時は、サッカーの部分を新たに切り抜くか、全部作り直すことで対応します。
3.反対側からも同じようにする
反対側からも同じ要領で鉢底ネットを切って乗せます。

向かい合った2枚を重ねる時は「互い違い」になるように、植物のむこうとこっちで上下を変えて重ねると、互いに押さえ合ってズレにくくなりますよ。
4.残ったスキマを埋める
まだ土が見えている場所やスキマがある場合は、そこを埋めるだけの小さなパーツを作ります。

切り取った残りの部分が使えるならそれを使い、大きさが合わない場合は新しく切り出して作りましょう。
小さなパーツはズレやすいので、隣接するネットと重なる面積が広くなるように、大きめに作るのがポイントです。また、重ね順の一番下にするといいですよ。
5.土の表面を全面カバーできれば完成
こんなかんじで、まずはブルーベリーの木の根元に鉢底ネットの設置が完了しました。
スキマ無くきっちりカバーできていますね。

ほかのプランターもやってみよう
ということで、残りのプランターも同じようにやってみましょう。
写真:左のボイセンベリーの木も先ほどと同じプランターなのでやり方はほぼ同じ。

ボイセンベリーは支柱を立てているので、そのぶんカットがちょっと複雑でした。
丸い鉢はこうするといいよ
この小さな丸い鉢では、ボイセンベリーの苗を育てています。
丸い鉢にあわせてカットするのは難しそうって思いますよね。
そんな時は「ダーマトグラフ」を使って鉢をトレースするといいですよ。

「ダーマトグラフ」はどんなところにも線が引ける特殊な色鉛筆です。裁縫で使うチャコペンの進化版みたいなもの。ガラス・金属・プラスチックなどに線を引けますよ。
こうして鉢底ネットに切り取り線を描けば、丸い鉢にぴったりな形にカットできますね。
まとめ:コガネムシ対策にお勧めです
今回は「鉢底ネット」を使ったコガネムシ対策についてご紹介しました。
この方法は低コストで・確実にコガネムシの産卵を防げるのでオススメですよ。

この方法は、ベリーの木など小さめの果樹や、バラなどに向いていると思います。
「鉢底ネット」を使うメリット
以前は「不織布」でコガネムシ対策をしていましたが、「鉢底ネット」に変えてみたらこんなメリットがありました。
- 着脱がかんたんなので、一部をはずして土の状態をチェックするのも容易。
- 雑草はネットのマス目から上に出てくるので、不織布よりも雑草を抜きやすい。
- 上にゴミが溜まったら、ペロッと剥がしてパタパタすればあっという間にキレイに。
というかんじで、管理がしやすくなりました。

大切な植物をコガネムシに枯らされないように、なんらかの対策をしておくことをお勧めします。
その方法の1つとして、私がやっている今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。
こちらの記事もぜひ参考に